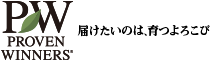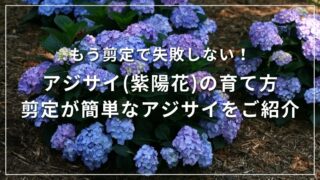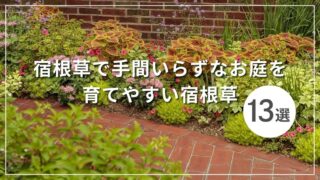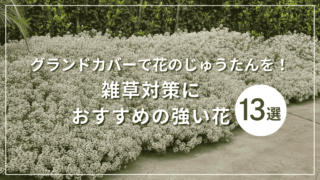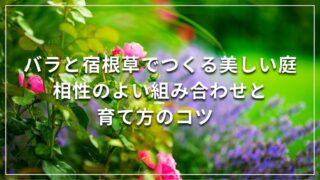どんなに元気な植物を育てていても、ガーデニングをしているとどうしても避けて通れないのが病気や害虫です。しかし、予め予防をすることで病害虫の発生を少なくすることもでき、症状が拡大する前に対策することで被害を最小限に抑えることもできます。
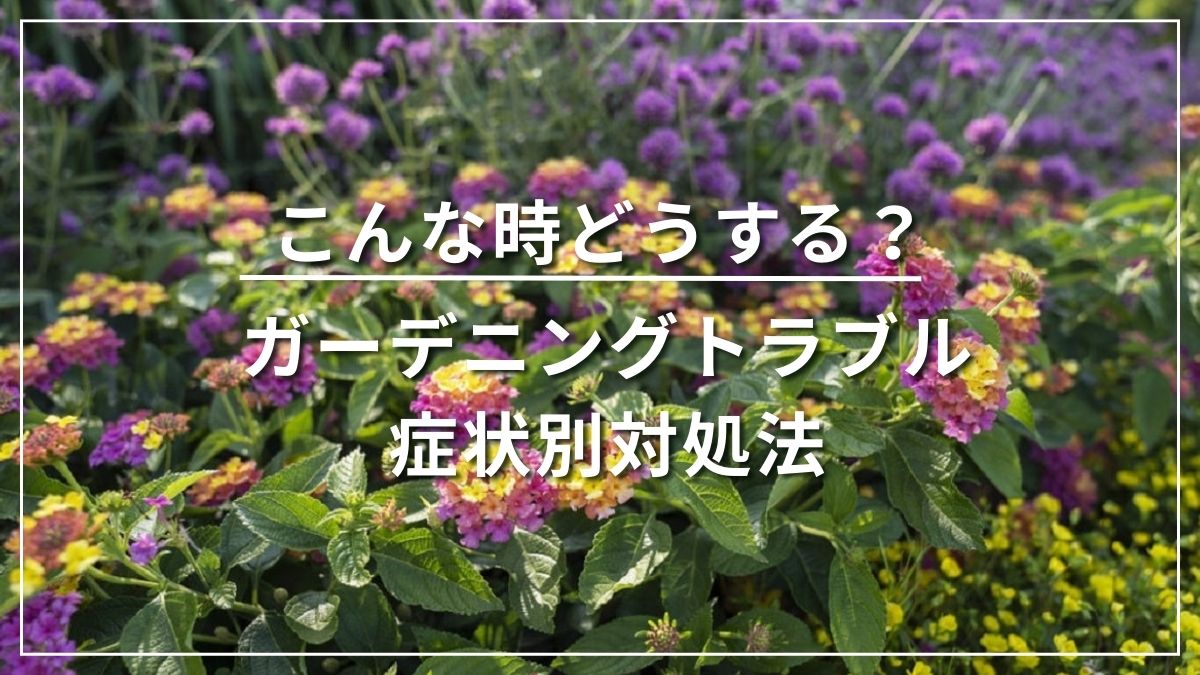
ガーデニングをする上で、よくある病害虫の被害を症状別にまとめてみました。早期発見や予防・対策にお役立てください。
発生している症状
葉に異常がある
茎に異常がある
花に異常がある
根に異常がある
全体に異常がある
病害虫別対処法
病気
斑点病(サーコスポラ)

斑点病(サーコスポラ)は、葉や茎に、淡褐色~褐色の斑点が生じる症状が見られ、症状が拡大すると葉が枯れる病気です。初期は古い葉で発生しやすいです。カビの仲間である糸状菌によって、春から秋に発生します。
雨や水やりなどの水滴で病気が広がります。冬は症状が見られなくなりますが、翌年も再発する可能性があります。落葉はきちんと取り除いて、翌年の再発を防いでください。
| 発生しやすい植物 | アジサイ、キク、ゼラニウムなど多くの植物 |
| 発生しやすい部位 | 葉や茎 |
| 発生しやすい時期 | 春から秋 |
| 予防方法 | 水やりの際に株元に水を注ぎ葉に水がかからないようにしましょう。地表面をマルチングして泥はねを防ぎましょう。薬剤をあらかじめ散布して、風通しのよい場所で育てるようにしましょう。 |
| 治療方法と拡散防止対策 | 病徴の見られた部位を取り除き、処分します。治療効果のある薬剤を散布しましょう。鉢植えの場合は、軒下などに移動してなるべく雨がかからないようにしましょう。 |
炭疽病

糸状菌(カビ)による病気で高温多湿時に発生しやすいです。葉などに灰色から黒褐色の斑点が発生し病斑部分が枯れて穴があいたり、病気が進むと植物が枯れてしまうこともあります。病斑の中心部分に小さな黒い粒がでえきることがあります。炭疽病は、広がりやすく株全体へ被害が拡大してしまうと治療が難しいので、早期発見と早めの対策が大切です。 病原菌は感染した植物や土壌中で生き残り、 翌年も発生する可能性があります。
| 発生しやすい植物 | シクラメン、シンビジウム、アジサイ、野菜、庭木など多くの植物 |
| 発生しやすい部位 | 主に葉。果実や茎、植物全体に広がることもあります。 |
| 発生しやすい時期 | 春や秋の長雨の時期 |
| 予防方法 | 薬剤をあらかじめ散布しましょう。混みあった枝は剪定し、風通しよくしましょう。肥料のうち窒素分をやりすぎないように注意しましょう。 水やりの際に株元に水を注ぎ葉に水がかからないようにしましょう。 地表面をマルチングして泥はねを防ぎましょう。 |
| 治療方法と拡散防止対策 | 病徴の見られた部位を取り除き、処分します。治療効果のある薬剤を散布しましょう。 |
黒点病(黒星病)

糸状菌(カビ)による病気です。葉や茎に黒い斑点ができます。病気にかかった葉は黒い斑点の周りから黄色く変色していき、葉が落ちます。
| 発生しやすい植物 | バラ、バラ科の果樹 |
| 発生しやすい部位 | 葉や茎 |
| 発生しやすい時期 | 梅雨と秋雨の時期 |
| 予防方法 | 水は株元から葉に水がかからないように与えましょう。地表面をマルチングして泥はねを防ぎましょう。予防薬剤を定期的に散布して、風通しのよい場所で育てるようにしましょう。 肥料のうち窒素分をやりすぎないようにしましょう。 |
| 治療方法と拡散防止対策 | 雨の跳ね返りで葉の裏から伝染し、被害が拡大していきますので病斑のできた葉は取り除きます。治療効果のある薬剤を散布しましょう。 鉢植えの場合は、軒下などに移動してなるべく雨がかからないようにしましょう。 |
うどんこ病

葉にうどんこを振りかけたような粉状の円斑が生じたらうどんこ病の可能性があります。徐々に葉全体に広がり、葉は変色し、萎れ、やがて枯死します。多くの葉に発病すると生育が悪くなります。
18℃付近となる春や秋によく発生します。冬は症状が見られなくなりますが、翌年も再発する可能性があります。
| 発生しやすい植物 | バラやイチゴ、キュウリなど多くの植物 |
| 発生しやすい部位 | 葉や花首 |
| 発生しやすい時期 | 春と秋の乾燥したとき |
| 予防方法 | 予防薬剤を定期的に散布して、日当たり良く風通しの良い場所で育てるようにしましょう。肥料のうち窒素が多すぎたりカリウムが不足するとかかりやすくなるので肥料はバランス良く与えてあげてください。 |
| 治療方法と拡散防止対策 | 病徴の見られた部位を取り除きます。風通しの良い場所に移して、うどんこ病に効果があるカリグリーンなどの薬剤を規定量に希釈して散布してください。カリグリーンは、オーガニックな薬剤です。 風通しのよい場所で育てているのにうどんこ病を発症している場合は、肥料のあげ過ぎで窒素過多になっている可能性も考えられます。肥料のあげ過ぎに注意して育ててください。 |
すす病
すす病とは、葉に炭のすすがついたような症状の病気で、葉が呼吸できない状態になってしまいます。アブラムシやカイガラムシ、コナジラミなどの害虫の排泄物にカビが付着して発生します。
| 発生しやすい植物 | 花木、観葉植物、トマト、キュウリなど多くの植物 |
| 発生しやすい部位 | 葉、幹、実 |
| 発生しやすい時期 | 夏から秋 |
| 予防方法 | オルトランなどの殺虫剤をあらかじめ散布して、害虫対策を実施します。 |
| 駆除方法 | 病徴の見られた部位を取り除きます。殺虫剤を散布して、再発を防ぎましょう。 |
立枯病

立枯病とは、初めは下葉や根元の茎が黄色になり、症状が拡大すると苗が倒れて枯れる病気です。病原菌はカビの一種で、土壌感染する病気です。春~秋の湿度の高い季節に発生します。
病原菌は被害植物上や土の中で越冬し翌年も再発する可能性があります。
| 発生しやすい植物 | コスモスやユーフォルビアなど多くの植物 |
| 発生しやすい部位 | 根や根元の茎、株全体 |
| 発生しやすい時期 | 春から秋の湿度の高いとき |
| 予防方法 | 水やりはなるべく朝にするようにしましょう。風通しの良い場所で育てるようにしましょう。連作は避けましょう。 鉢植え土は再利用せずに新しいものを利用するようにしてください。地植えの場合は春、秋の植えつけ前に土壌消毒しましょう。 |
| 治療方法と拡散防止対策 | 発病した株はビニール袋に入れて、袋を閉じた状態で除去します。また、他の植物への感染予防のため、薬剤を散布します。 |
灰色かび病(ボトリチス)

灰色かび病(ボトリチス)は、老化した花弁や傷んだ葉先、茎、地面に接した葉柄などが水浸状に腐敗する病気です。症状が拡大すると灰色のかびに覆われます。花弁は、斑点が多数生じ、やがて枯れます。
18℃付近の春や秋に、多湿な状態が続くとよく発生します。

花や蕾に部分的に茶色い染みが発生している場合も、灰色かび病(ボトリチス)が原因かもしれません。
| 発生しやすい植物 | アジサイ、シクラメン、バラなど多くの植物 |
| 発生しやすい部位 | 花、つぼみ、果実、茎、葉など地上部のほとんど |
| 発生しやすい時期 | 春と秋の湿度の高いとき |
| 予防方法 | 灰色かび病は高温多湿を好むので、水やりはなるべく朝のうちに株元に与えるようにしましょう。鉢植えの場合は水はけのよい土を使用しましょう。風通しの良い場所で育てるようにしましょう。硝酸カルシウムをあげましょう。カルシウムは細胞壁の構成成分のひとつであり、硝酸カルシウムをあげることで植物が強健になり、葉も大きくなります。窒素分が多いと株が軟弱に育ち病害虫が侵入しやすいので肥料のあげ方に注意しましょう。 |
| 治療方法と拡散防止対策 | 病徴の見られた部位は、見つけ次第すぐに取り除き処分します。薬剤を散布して、再発を防ぎましょう。 |
疫病(フィトフィトラ)

病原体はフィトフィトラというカビの仲間で、梅雨や秋雨で雨が続くと多発しやすいです。植物全体に発生し、症状は多岐にわたります。葉では葉脈に沿って斑点が拡大します。白いカビが生えたり、枯れたりします。根から感染して、根腐れが起こります。遊走子により水媒伝染し、罹病植物中や土の中で越冬します。
| 発生しやすい植物 | シクラメン、ガーベラ、ニチニチソウ、トウガラシなど多くの植物 |
| 予防方法 | 土は毎年新しいものを利用するようにしてください。水のあげ過ぎに注意して育てましょう。底面潅水の使用を控えて水の再利用は避けましょう。 |
| 治療方法と拡散防止対策 | 発病した株はビニール袋に入れて、袋を閉じた状態で除去します。また、他の植物への感染予防のため、薬剤を散布します。 |
白さび病

白さび病は、さび病菌と呼ばれるカビの一種によって発生する病気です。春と秋の雨が多い時期に発生する傾向があります。初めは黄色味のかかった白色の斑点が葉の裏にでき、徐々に斑点が大きくなり盛り上がったいぼのようにもなります。そのため、葉がゆがんだり巻かれたりする症状が発生します。
| 発生しやすい植物 | アジサイ、ぶどうなど |
| 発生しやすい部位 | 葉 |
| 発生しやすい時期 | 春と秋の湿度の高いとき |
| 予防方法 | さび病菌は多湿を好むので、水のあげ過ぎに注意しましょう。春と秋に薬剤を散布し、風通しのよい場所で育てるようにしましょう。 |
| 治療方法と拡散防止対策 | 病徴の見られた部位を取り除き、処分します。多くの葉に症状が出ている場合は、植物が育つ範囲で葉を取り除くようにしてください。 |
黒かび病

サンブリテニア(ジャメスブリテニア)で見られる病気で、主に枝分岐部や葉先で黒褐変症状が観察され、その後枯死することがあります。黒かびという糸状菌が雨や風で飛散し、伝染します。
春~秋に、湿度が高まると発生しやすくなります。冬は症状が見られなくなりますが、翌年も再発する可能性があります。
| 発生しやすい植物 | サンブリテニア(ジャメスブリテニア) |
| 発生しやすい部位 | 葉や茎 |
| 発生しやすい時期 | 春と秋の湿度の高いとき |
| 予防方法 | カビは高温多湿を好むので、水やりはなるべく朝にするようにしましょう。風通しの良い場所で育てるようにしましょう。 |
| 治療方法および拡散防止対策 | 病徴の見られた部位を取り除き、ビニール袋にいれて、すみやかに処分します。発病株を触った後に作業をする時は、必ず手や道具(ハサミ、カッター等)を消毒するようにします。他の株への感染予防のため、薬剤散布しましょう。 |
軟腐病
軟腐病は、細菌が原因で、特有の悪臭を発します。根や葉にできた傷口や地際部から感染し、細菌が繁殖して養水分の通り道を塞ぎ、地際部から腐って溶けたようになる病気です。株がしおれて倒伏することもあります。

病原菌は感染した植物や土壌中で生き残り、土壌伝染します。
| 発生しやすい植物 | ハクサイ、シクラメン、ランなど葉物野菜や球根植物 |
| 発生しやすい部位 | 地際部から株全体 |
| 発生しやすい時期 | 春から秋、特に梅雨や秋雨の時期 |
| 予防方法 | 雑草など発生源になるものはできるだけ除去しましょう。土壌が多湿にならないように水管理に気を付け風通しのよい場所で育てるようにしましょう。肥料分のうち窒素が多すぎると軟弱になりやすいので気を付けましょう。薬剤をあらかじめ散布しておきましょう。 |
| 拡散防止対策 | 発生した軟腐病には薬剤が効きにくいので発病した株はビニール袋に入れて、袋を閉じた状態で除去します。また、他の植物への感染予防のため、薬剤を散布しましょう。 |
根頭がんしゅ病

根頭がんしゅ病とは、根や茎などにこぶが生じ、症状が進行すると茎葉の生長が衰え、委縮し、放っておくとやがて枯死することがある病気です。休眠胞子の状態で土壌中に長期間生存し、土壌や樹液などで植物の傷口から感染します。感染するとほぼ治療ができない病気です。
双子葉植物に感染する特徴を持ち(イネ科の植物など単子葉植物には感染しません)、生育温度は14~34℃で、春になり暖かくなると症状が見られることが多くあります。
| 発生しやすい植物 | バラ、キク、マーガレットなど |
| 発生しやすい部位 | 地際部 |
| 発生しやすい時期 | 春 |
| 予防方法 | 新しい土を使って、水はけのよい土壌で育てましょう。 |
| 拡散防止対策 | 感染した株は回復しないので、こぶを取り除こうとしないでください。病徴の見られた苗はビニール袋にいれて、すみやかに処分します。二次感染力が強いので発病株を触った後に作業をする時は、必ず手や道具(ハサミ、カッター等)を消毒するようにします。 |
モザイク病(ウィルス病)

モザイク病(ウィルス病)とはウィルスの一種で、薄い緑色の斑点ができたりモザイクな状態ができる症状です。被害が拡大すると、葉の縮れなどの変形や濃い斑点などを生じるようになります。
主にアブラムシなどを媒介して伝染するため、アブラムシが発生しやすい春や秋にかけて伝染します。アブラムシの他にも、アザミウマ、コナジラミ、ハダニなどによって媒介されることがあります。
| 発生しやすい植物 | バラ、キク、パンジー、ペチュニアなど |
| 発生しやすい部位 | 葉 |
| 発生しやすい時期 | 春、秋 |
| 予防方法 | アブラムシの発生を防ぐために、風通しの良い場所で育てましょう。 |
| 拡散防止方法 | モザイク病(ウィルス病)に感染すと治療する方法はありません。病徴の見られた苗はすみやかに処分します。発病株を触った後に作業をするときは、必ず手や道具(ハサミなど)を消毒するようにします。発病した植物を置いていた場所もあわせて消毒してください。 |
生理障害
チッ素欠乏症

下の葉が黄色に変色してきた場合は、チッ素欠乏症の可能性があります。チッ素は、肥料に含まれる大量要素の1つで、植物の体を構成するタンパク質やアミノ酸の元になるものです。下葉が黄色になるのは、肥料が足りていないサインの1つです。
| 予防方法 | 肥料を施す量を守りながら、肥料を定期的にあげるようにしてください。梅雨の時期など長雨で液体肥料が流れやすくなる季節は、特にたっぷりあげるようにしてください。 |
| 拡散防止方法 | チッ素を含む肥料をあげてください。速やかに吸収される液体肥料をあげるのがおすすめです。 |
カルシウム欠乏症

緑葉が茶色になったり葉の形がゆがんできたりしたら、カルシウム欠乏症の可能性を疑ってみてください。
カルシウム(Ca)は、根が生長するのを助け、病害虫に対する抵抗力をつける働きがあります。肥料が足りていないサインの1つです。
| 予防方法 | 肥料を施す量を守りながら、肥料を定期的にあげるようにしてください。梅雨の時期など長雨で液体肥料が流れやすくなる季節は、特にたっぷりあげるようにしてください。 |
| 拡散防止方法 | カルシウムを含む肥料をあげてください。カルシウムは植物体内で移動しにくい成分なので不足している場合は、水溶性カルシウムの散布が有効です。 |
高温障害

夏場の高温時、特に梅雨明けの急激な気温上昇時には、植物の光合成が阻害されたり、水分や養分の吸収がしにくくなったりして、生理障害が起きることがあります。
アジサイでは新芽が縮れて葉形がゆがんだり、ゼラニウムでは葉色が白く抜けたようになったり、トマトでは実が出来づらくなるなど、様々な症状があります。
| 発生しやすい植物 | アジサイ、ゼラニウム、トマトなど多くの植物 |
| 発生しやすい部位 | 葉や果実 |
| 発生しやすい時期 | 梅雨明け後など夏の高温時 |
| 予防方法 | 夏場の暑い時期のみ日陰の涼しいところで管理したり、遮光ネットなどで遮光しましょう。トマトは早朝の涼しい時間帯にトマトトーンなどのホルモン剤を用いて着果を促しましょう。 |
| 対策 | 一般的には涼しくなるにつれ株の状態は回復していきますが、可能であれば暑い時期のみ涼しい環境へ移動したり、遮光ネットで遮光しましょう。 |
害虫
アオムシ・イモムシ・毛虫類

葉っぱが食われていたり、黒や緑色の粒状の糞が落ちていたら、そのあたりにアオムシやイモムシ・毛虫がいる可能性があります。アオムシやイモムシ・毛虫類は卵・幼虫・蛹・成虫の完全変態で、春から秋にかけて数回発生します。

| 予防方法 | 葉裏や枝をよく観察して卵のうちに発見して取り除きましょう。薬剤で積極的に防除する場合はオルトランなど、効果が持続するタイプの殺虫剤をあらかじめまいておくと効果的です。 |
| 対策 | 見つけたらすぐに捕殺するのが一番の対策です。小さな幼虫が残っている可能性もあるので、植物に園芸用殺虫剤をかけておきましょう。 チャドクガ・イラガなどは、一カ所に集まっている孵化直後に、葉ごと切り落として処分します。 |
アブラムシ

アブラムシの繁殖期は、4~6月と9~10月です。雌だけで増えることができる(単為生殖)ので繁殖力が旺盛です。アブラムシは、植物の栄養分を吸い取ってしまうので早めに駆除したい害虫です。アブラムシは病気(ウイルス病)を運んだり、排泄物にカビが生えて葉が黒いすすに覆われたようになる「すす病」を誘発することもあります。 アブラムシの成虫の大きさは、1~4㎜程度になります。
アリが植物を上り下りしているとアブラムシがいる可能性があります。発生初期で対処すると、被害の拡大を食い止めることができます。注意して葉を観察してみてください。
| 予防方法 | 鉢は、風通しの良い場所に置きましょう。アブラムシは黄色い色に誘引される性質があるので、黄色の粘着テープを吊るしておくと発生予防に役立ちます。光を苦手とするので、株元にアルミホイルを敷いておくと、忌避できます。 積極的に防除する場合はオルトランなどの浸透移行性で効果が持続するタイプの殺虫剤をあらかじめまいておきましょう。暑い時期のみ日陰の涼しいところで管理したり、遮光ネットなどで遮光しましょう。トマトは早朝の涼しい時間帯にトマトトーンなどのホルモン剤を用いて着果を促しましょう。 |
| 対策 | アブラムシは、単為生殖で、雌が1匹いれば増え続けることができる害虫です。アブラムシがたくさんついてしまった部分は切り落とし、アブラムシに効くアーリーセーフなどの薬剤を規定量に希釈して散布してください。 |
カイガラムシ

カイガラムシは5~7月に発生することが多いです。植物から栄養を横取りして、弱らせてしまいます。葉の表面がテカテカしていたり、ベトベトしていたらカイガラムシが発生している可能性が考えられます。注意して葉を観察してみてください。

| 予防方法 | 鉢は、風通しの良い場所に置きましょう。 |
| 対策 | 植物の茎に小さな球状のものや白く平べったいものがついていたら、歯ブラシやへらなどでこそぎ落としましょう。成虫は足が退化しているため、植物からはがすことで駆除できます。但し成虫は薬剤が効きにくくなるので、幼虫のうちに駆除しておくことをおすすめします。 カイガラムシに効く薬剤を散布しましょう。 |
ハダニ

ハダニは梅雨明け頃から夏場にかけて、高温で乾燥している場所に出やすく、雨の当たらないベランダなどでよく見られます。
初めは葉の裏にほこりがついているように見え、次第に葉の表が白い点に覆われていきます。植物の葉の上に無数の白い点が現れたらハダニが発生している可能性が考えられます。放っておくと葉の全体に症状が拡がり、枯れてしまいます。

ハダニは、0.3~0.5㎜くらいの小さい虫で、特に葉裏をよく観察すると肉眼では赤や黒の点のように見えます。ハダニはクモの仲間で、数が増えると糸で葉がからまってきます。葉をこするように触ると、ざらざらした感触です。
| 予防方法 | ハダニは水に弱い性質があるので、葉っぱの表裏にしっかり水をかけると効果的です。ベランダや室内で育てている植物の場合は、週に1回程度霧吹きで葉に水をかける葉水をすると効果的です。 |
| 対策 | ハダニがたくさんついてしまった部分は切り落とし、ハダニに効く薬剤を散布しましょう。 |
アザミウマ(スリップス)

アザミウマは、多くの花、野菜、果樹や雑草に寄生します。葉や花にかすれたような白色や褐色の斑点が現れたり、花色がかすれたりしたら、アザミウマ(スリップス)の食痕の可能性があります。どこにでもいる害虫ですが、近くに雑草が繁茂していたり、野菜畑、果樹園が近くにある場合には注意が必要です。

アザミウマには多くの種類があり、黒色のネギアザミウマやヒラズハナアザミウマと黄色のミカンキイロアザミウマやミナミキイロアザミウマが代表的です。 アザミウマは植物に傷を付けて吸汁するので、ミカンやブドウなどの果実では被害箇所がカサブタ状になる場合があります。アザミウマの成虫の大きさは、1~2㎜程度になります。
| 予防方法 | アザミウマは非常に多くの植物に寄生します。そのため、雑草など発生源となるものはできるだけ除去し、咲き終わった花などは摘むようにして発生源を作らせないように予防してください。鉢は、風通しの良い場所に置きましょう。アザミウマは青色に誘引される性質があるので、青色の粘着テープを吊るしておくと発生予防に役立ちます。 積極的に防除する場合はオルトランなどの浸透移行性で効果が持続するタイプの殺虫剤をあらかじめまいておきましょう。 アザミウマ(スリップス)は蕾に侵入して加害するので、殺虫剤で予防するタイミングは蕾の時期になります。 |
| 対策 | 気が付かないうちにアザミウマ(スリップス)が蕾に侵入している場合、開花して花弁が展開すると花弁の縁が茶色くなっていたり、花弁に筋状の傷が入っていたりします。そのような被害を受けた花は摘み取り、念の為、アザミウマ (スリップス) に効く薬剤を散布して被害の拡大を抑えましょう。 |
ナメクジ・カタツムリ

もし、植木鉢の周りや葉の上などにテカテカと光るスジのようなものがあれば、それはナメクジが這った跡です。しっかり予防しないと、せっかくの新芽を食べられてしまい、株は大きく育っているのに全く花が咲かないということもあります。

飲み残しのビールでトラップを仕込む方法も効果的です。ビールを容器に入れて置いておくと、その匂いにおびき寄せられます。天敵は、コウガイビルです。食害するナメクジやカタツムリを食べてくれる益虫になるので、間違えて駆除しないようにしましょう。
| 発生しやすい植物 | 花全般 |
| 発生しやすい部位 | 花、葉 |
| 予防方法 | ナメクジ・カタツムリの隠れ家になるので鉢は地面に直接置かないように、枯葉は溜まらないように定期的に取り除くようにしましょう。また過湿にならないように過度な水やりは避けるなど、ナメクジ・カタツムリが住み着きにくい環境を整えましょう。 |
| 対策 | ナメクジ・カタツムリは雨降りの時や夜の間に這い出てきますが、それ以外の時は鉢底や落ち葉の下などに隠れています。誘引殺虫タイプのナメクジ駆除剤をあらかじめまいておびき寄せて退治しましょう。同時にナメクジは鉢の裏やウッドチップの間などジメジメ湿った場所に隠れていますので見つけたら捕殺しましょう。 |
ヨトウムシ

一夜にして葉が大量に食われたのに虫がいない!というような被害が出る場合は、ヨトウムシの仕業である可能性が高いです。ヨトウムシとはヨトウガの幼虫で、夜活動する大食漢のイモムシです。葉にかじられた跡のような穴が開いたり、葉が薄皮だけになって白っぽく変色したり、黒い粒のような糞が見られたら要注意です。

昼間はたいてい葉裏や株元などで寝ているので姿が見えないのですが、少し探すと見つかります。大きくなると殺虫剤が効きにくくなるので、卵や幼虫の間に見つけたらすぐに捕殺しましょう。幼虫のサイズは2~3cm程度です。 4月~6月、9~11月に活動が活発になります。
| 予防方法 | オルトランなどの浸透移行性の殺虫剤をあらかじめまいておきましょう。 ヨトウガ(ヨトウムシの成虫)が卵を産みつけるのは3~5月です。卵は乳白色で2×2cmぐらいの塊となっています。葉の裏などに卵を見つけたら、葉ごと取り除くようにしてください。 |
| 対策 | 見つけたら捕殺しましょう。オルトランなどの浸透移行性の殺虫剤をまいておきましょう。 |
ハマキムシ

葉がクルクルと丸まっているような場合は、ハマキムシ(葉巻き虫)の仕業である可能性が高いです。ハマキムシとはガの幼虫で、丸めた葉の中に隠れて、葉やつぼみを食べます。

数cmしかない小さい幼虫自体を見つけるよりも、幼虫が吐き出した糸で数枚の葉をくっつけていることがあり、その状態を見つける方が簡単です。
| 予防方法 | オルトランなどの浸透移行性の殺虫剤をあらかじめまいておきましょう。 |
| 対策 | クルクルと丸まった葉ごと取り除いてください。 |
コガネムシ、ネキリムシ

それまで元気に育っていた植物の生育が急に止まり、でも特に病気にやられているようには見えない時は、根が傷んでいる可能性があります。鉢植えであれば根の様子を見るためにも植え替えをしてみましょう。

その際、鉢土の中から丸くなった乳白色の幼虫がゴロゴロ出てくる場合はコガネムシ幼虫による根の食害が原因と考えれらます。また害虫の姿が見えないのに定植直後の苗の地際の茎が噛み切られている場合はネキリムシによる被害が考えられます。ネキリムシは昼間は土の中に潜んでいて、夜の間に地上部に出てきて苗を食害します。
| 予防方法 | 毎年コガネムシの幼虫の被害が少しでもある場所であれば、植付け前にダイアジノンをあらかじめ土に混ぜ込んでおきましょう。鉢植えの場合は、年に一度は鉢の植え替えをして根の様子を確認するようにしてください。ネキリムシ対策にはネキリベイトなどの誘引殺虫剤を株元に散布することで被害を防げます。 |
| 対策 | 周辺のできるだけ多くの土(鉢であれば鉢の中の全ての土)を耕してましょう。耕した際に出てきた幼虫は見つけ次第捕殺しましょう。 |
バッタ

春になり気温が高くなるとバッタが発生し始め、夏や秋の植物を食害します。バッタは、花苗、野菜、小さな昆虫などありとあらゆるものを食べ、植物の全体を食べ尽くしてしまうほどの食いしん坊です。一般的な庭で見るバッタの多くはオンブバッタやトノサマバッタです。
| 予防方法 | バッタを見つけ次第、被害が出る前に捕殺するようにしましょう。 |
| 対策 | 人的被害はないものが多いので捕まえて退治するか、殺虫スプレーを使用するなどして駆除しましょう。 |